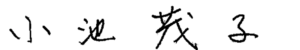理事長メッセージmessage
MESSAGE

小池 茂子
青山学院大学大学院文学研究科教育学専攻博士後期課程単位取得済退学(文学修士)。現在、聖学院大学人文学部教授。
2018年度より聖学院大学学長補佐、副学長、人文学部長、大学院文化総合学研究科長を歴任。2023年4月より学校法人聖学院理事長、聖学院大学学長に就任。
守り続けていくものと、 進化していくもの
仕える視座を持ったリーダーを育てる
2023年、学校法人聖学院は、「第2期聖学院ビジョン(2023~2027年度)」を策定いたしました。私どもの法人が目指すビジョンには、変えなければならないことと時代が変化しても変わってはならないものがあると考えています。変わってはならないもの、それは聖学院の建学の精神「神を仰ぎ 人に仕う」を体現した人を育て社会に送り出していくという使命です。
人に仕えるためには確かな知識や技能を持っていなければいけませんし、そのためには時代の変化が求める能力を各人がしっかりと習得していく必要があります。同時に、自分の持っている良さを自己利益のためだけでなく、他者や社会のために喜んで差し出せる人、他者と共に課題解決に当たっていける人間性を持ったリーダーを世に送り出すこと、これが聖学院の教育が目指すゴールです。
私どもの法人の下には、幼稚園から大学・大学院まで、それぞれの学校が特色ある教育を展開していますが、本学院の特色ともいえるキリスト教に基づく教育には、今日人類が直面している人間の尊厳や人権の問題、多様な背景を持つ人たちと共に生きる社会の実現等、現代社会の課題や自分の生き方を探求する手掛かりがあります。教室の中に留まることのないクラブ活動や社会貢献活動、礼拝を通じた聖書の問いかけが、そこに学ぶ者の自己形成に働きかけ、これを通じて深くものを探求し行動する人間を育てる。ここに聖学院の教育意義があると考えます。
地域社会に貢献する
学校法人聖学院の下にある学校は、東京・駒込の地で120年の歴史を形づくり、埼玉県の上尾・さいたまの地でも半世紀以上の歴史を紡いでまいりました。人間は周囲の者が持っている価値観や生活する姿から多くの感化を受けて育つ存在です。駒込の地で、地元の方々に温かく見守られ、時に褒められ、時に叱られることを通じて、園児、児童、生徒たちは育てられてまいりました。彼らの記憶の中には、駒込駅から商店街を通ってそれぞれの学校に通った風景が良き思い出として残っていくはずです。
埼玉県上尾市とさいたま市の市境にある大学、みどり幼稚園も地域と共にその歩みを進めてまいりました。みどり幼稚園は聖学院大学のキャンパスに隣接する幼稚園として、また質の高い教育を行う幼稚園として地域の皆様から高い評価をいただいております。大学も周辺の基礎自治体や経済会と包括連携協定を結び、リカレント講座や総合研究所の研究会、大学院など、年齢も職種も異なる社会人が昼夜にわたり来学しています。これからも大学が有している知的、文化的、人的な資源を地域貢献のためにひらき、同時に地域の支援もいただきながら教育・研究の向上を目指してまいります。
それぞれの学校が、地域に貢献しながら地域によって支えられていくという良き循環をさらに進め、地域にとって聖学院の各学校がなくてはならない存在となるよう取り組んでまいります。
点検評価の質を高め
ビジョンの達成を目指す
聖学院ビジョン第1期を終え、第2期ビジョンでは新たな評価システムを加えることになりました。今回の聖学院ビジョンでは「5つの重点実施項目」を設定し、この指標に基づいて法人及び各学校が2023年度から向こう5年間で取り組む事柄を明確にしました。また、これについて年度ごとに定性的・定量的視点から点検評価を行い改善につなげてまいります。
5つの重点実施項目の中で最も重視しているのは教育・研究の質向上です。これまでも聖学院の教育といえば、キリスト教を通じた人格教育、英語教育、ICT教育、グローバル教育、サステイナブルな社会実現に向けた課題解決型学習やボランティア活動等が高い評価を得てまいりました。聖学院の下にある学校群が特色ある教育を展開していくために、駒込キャンパスには教育デザイン開発センターがあり、同センターのプロジェクトとして、聖学院小学校と女子聖学院中高、聖学院中高の3校連携によるSDGsプログラムなどが実施されました。また、大学には教育開発センターがあり、特色ある全学共通プログラムや初年次教育などのカリキュラム検討・開発が行われ、大学IR室(Institutional Research)では、学生たちの生活満足度や学修成果の定量的分析とそれに基づく教育改革といったPDCAサイクルが構築されています。
これからも駒込の教育デザイン開発センターと大学の教育開発センター機能を充実させ、各校が質の高い教育を実現し、その取り組みについて評価も含めた情報公開を行い広く社会の信頼を得てまいります。
少子高齢社会の進展や将来展望を描くことが難しい時代といわれる中で、私どもの学校法人にも課題がありますが、第2期聖学院ビジョンを掲げ、神さまから与えられた教育という使命を力強く進めて参りたいと考えています。
ご父母のみなさま、卒業生、ご関係の皆様におかれましては、日頃から本法人のもとにある学校をお覚えいただき、多くのご厚意を賜りましたことをここにお礼申し上げます。今後も、本法人の下にある各校が良い教育・研究を進めていくために、一層のご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。