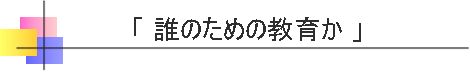 |
||
[2/4ページ] |
||
■高度成長期のエリート養成教育 |
||
朝日新聞の『天声人語』に、小学校の宿題で、「わたしの長所」という作文を出した話が出ていました。PTAから「長所なんか放っておけばいいんだ。教育っていうのは短所を直すのが教育でしょう。だから宿題は『わたしの短所』でないといけないのではないか」とクレームがくるというのです。現に「わたしの短所」という宿題を出すと、小学生・中学生はいっぱい書いてきます。ところが「わたしの長所」という宿題を出したら全然書いてこないのです。これでは子どもたちが伸びるはずはありません。「自分は駄目な人間。ここも駄目、あそこも駄目」という人間が「よし、いい人間になろう」と思えるはずがないです。短所を直すことは面白くないことです。長所があって「『これ』を伸ばせば自分は人から認められ、能力を発揮できる。よしこれを伸ばそう。でもそれだけではバランスが悪いぞ。ほかの点も人並みにはやっておきたいぞ。」という思いになって初めて、短所の方を直していこうという気持ちが起こってくるわけです。初めから短所だけ指摘して、「それを直せ」という教育では子どもの人間性が伸びるはずはありませんが、父母達は「短所を直すのが教育である」と思い込んでいます。先生方の多くもそう思い込んでいたのでしょう。だから短所ならいっぱい書けるという人間になってしまったのです。これが、今の子どもたちに大きなひずみをもたらしている理由だと思います。
|
||
| 体制を変えてきたのですが、日本では市民から変えていくという盛り上がりはありませんでした。日本ではブルジョア革命もプロレタリア革命も起こりませんでしたが、これは人間としての成熟をもたらす点で非常にマイナスです。 エリート養成教育をしたお陰で日本は急激に経済発展を遂げて、大国と肩を並べるようになりました。ただ、思い上がりが強かったために戦争をして負けました。そこで、もう一度振り出しに戻って市民の力で国を作る方向に進もうと、憲法は立派な精神で作りました。しかし、経済的に壊滅状態にあったので、今度は経済の面で追いつけ追い越せという形で戦後の時代がありました。時代によって最初は船、やがて、車といったそういった重厚長大と言われる特定の基幹産業に、人材と資本を集中的に投入しました。よくいう「経済至上主義」です。これで日本は戦後の昭和20、30、40年代に驚異的な経済成長を遂げました。ですから、日本の発展を考えれば、それもまた正しかった路線であります。したがって、教育もやはりエリート主義でした。非常に頭が良く、海外の進んだ経済の技術をすぐ取り入れて、うまく日本風にアレンジをする人間を、戦前に引き続いて戦後も産業界は必要としたということです。そこで、学校ではたくさんの科目について記憶力がよく、理解が早い人材が求められました。追いつけ追い越せですから、自分の頭で考えて、新しい物を作り出す必要がないわけです。自分の頭で考えて「どうもこの体制はおかしいぞ」などと言い出だして体制を変えようとする人間は経済発展にとっては邪魔ですので、企業は「おとなしくて頭のいい人間」をどんどん採用しました。それは非常に成果があったわけで、そういう人たちがどんどん欧米の技術を取り入れ、日本の急激な経済発展をリードしてくれました。エリートが引っ張ってくれてそれについていけば、日本の経済は発展するので、他の人はそこそこでいいと考えたのでしょう。教育の全体が東京大学を頂点とした偏差値というひとつの価値基準による学校の階層化ができてしまいました。みんながせっせと少しでも上になるように目指して、親も子供を勉強させ、子どももその中で競争してきたというのが、戦後の30年間ほどの姿であったろうと思います。 |
||
